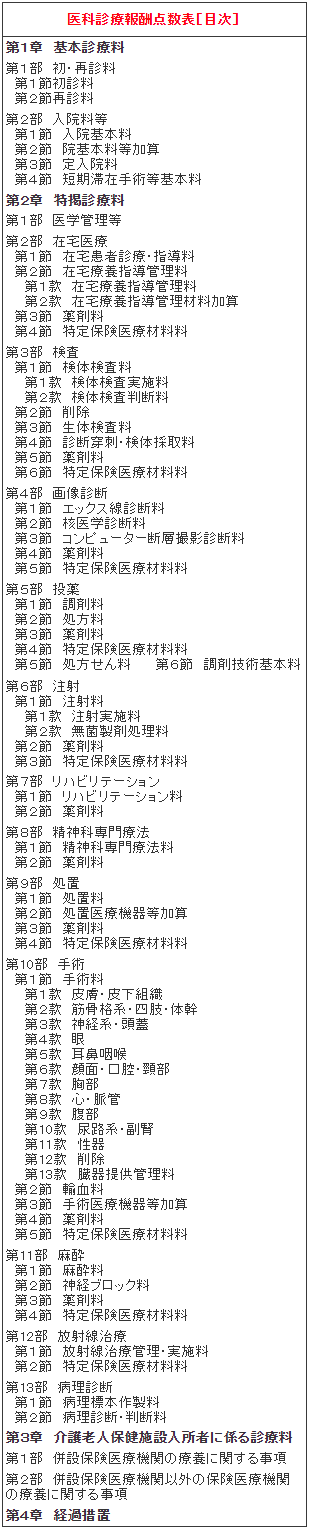診療報酬とは何か?
患者が病院に来院すると、医師は診断・治療などの医療行為を行います。
その医療行為の対価として、医療機関より請求されたレセプトを保険者が審査し、OKであれば診療報酬という形で支払われるお金です。
医療機関を運営するための大きな収入源となっており、診療報酬請求業務は医療事務が担います。
医療事務が診療報酬を算出する際、診療報酬点数表を使用して計算を行います。
このページでは、診療報酬点数表の構成を紹介していきたいと思います。
個別での出来高払いという方式で診療報酬の支払いは行われます。
この方式では病院で医師をはじめとする医療専門職が患者に施したひとつひとつの医療行為を評価し、金額換算して点数にし一覧表のような形式でまとめられています。
患者個々に実施した診断・検査・投薬・治療などの医療行為を点数表に従って点数換算し、算出した総計点数に診療単価の10円を掛け算した金額が支払われる診療報酬の金額になります。
この作業で使用される点数表を専門用語で「診療報酬点数表」と呼びます。
健康保険法の規定・基準にて診療報酬算定方法が取り決め事項として定められています。
また厚生労働大臣が、療養の給付に必要となった金額を定める決まりになっています。
診療報酬点数表とは何か?
健康保険法に準じて診療報酬点数表が最終的に決められますが、調剤・医科・歯科の3つに診療報酬点数表は区分されています。
これ以外にも薬価基準と材料価格基準が規定されており、これらは厚生労働大臣が規定するものとなっていて、両基準とも公定価格として決定されます。
ちなみに、薬価基準とは、保険診療で医師が処方する医薬品に関しての価格及び範囲を規定した基準を指します。
また、材料価格基準とは、点数表で規定されている特定保険医療材料料として計算される医療材料に関しての価格及び範囲を規定した基準を指します。
先ほど、診療報酬点数表は調剤・医科・歯科と3区分されているといいましたが、この中の医科点数表については、2006年(H18年)4月の法律改正以前では、点数表は医科診療報酬と老人医科診療報酬の2種類に分かれていましたが、現在は医科診療報酬点数表に一本化され運用されています。
健康保険法と高齢者医療確保法に準じて規定されているのが医科診療報酬点数表です。
民間会社に勤務する会社員が加入している健康保険、公務員が加入している共済組合、船員が加入している船員保険などの被用者保険、国民健康保険、公費負担医療においても、医科診療報酬点数表に基づいて金額が算出されます。
医科診療報酬点数の構成
平成30年3月現在の医科診療報酬点数表の構成は、下記のような目次で各内容が規定されています。