感染症予防・医療法は、患者の人権を守り、感染症の未然予防とまん延を防ぐための対策をトータル的に・計画性をもって行えるようにするために制定された法律になります。
このページでは、医療事務として理解しておくべき感染症の区分と対象となる疾病の種類について解説していきます。
感染症予防・医療法とは何か?
自然環境として水分、土壌、大気、動植物などが存在しますが、その環境には様々な病原体が生存しています。
ウイルス、細菌、寄生虫、カビなどは、感染症を発症させる原因となる病原体で、それらの病原体が人体に入り込むことで発症する疾患を感染症と呼びます。
感染症予防・医療法(感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律)の目的は次の2点です。
- 感染症を発症した患者の人権を保護する。
- 感染症の予防及びまん延を防ぐための対応策を総合的観点に基づき計画性を担保して実施する。
1999年4月より感染症が発生した場合に、より的確・迅速に対処できるようにするため、伝染病予防法、性病予防法、エイズ予防法が廃止され、その3つの法律を一本化して施行されることになりました。
感染症の分類と種類について
感染症予防・医療法において令和3年3月3日改正の感染症法における分類一覧では、感染症は次の8つに区分されており、それぞれの分類においても疾病名が指定されています。
- 一類感染症
- 二類感染症
- 三類感染症
- 四類感染症
- 五類感染症
- 新型インフルエンザ等感染症
- 新感染症
- 指定感染症
疑似症患者の法的扱い
1類感染症の疑似症患者は1類感染症の患者とみなされ、2類感染症の中で政令で規定される疑似症患者は、2類感染症の患者とみなされて感染症予防・医療法に基づいた適用対象となります。
疑似症患者とは、病気の症状はあるが病原体による正式な診断が行われていない者を指します。
無症状病原体保有者の法的扱い
1類感染症の無症状病原体保有者は、1類感染症の患者とみなされ、新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者は、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなされて、感染症予防・医療法に基づいた適用対象となります。
無症状病原体保有者とは、感染症の病原体は体内に保有しているが、感染症の症状が発現していない人を指します。
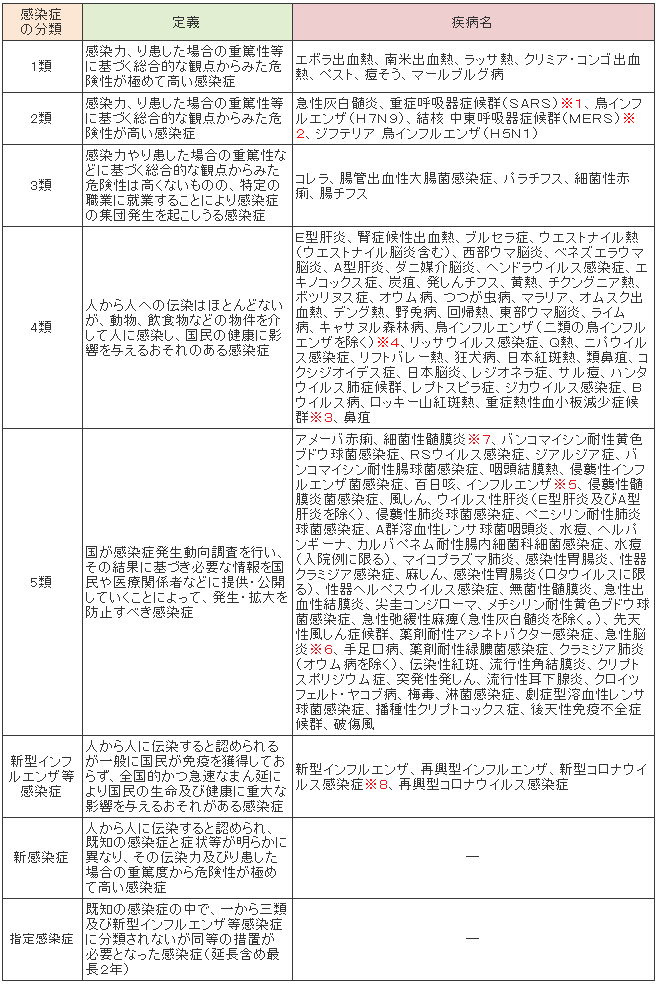
京都市情報館「感染症法における分類一覧(令和3年3月3日改正)」による





